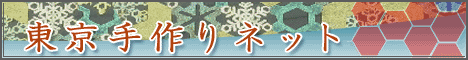東京ゆかた工業協同組合 03−3661−3862 103−0024 中央区日本橋小舟町9−16 関連リンク 清水染工さんのページ
 |
浴衣という言葉は、 平安時代初期の「延喜式」(えんぎしき)の中にもみえますし、 「和漢三才図会」(正徳3年,1713年)に 「浴衣(よくい)、内衣(ないい)、明衣(めいい)和名 湯加太比良(ゆかたびら)、 俗に由加太という浴帷子(ゆかたびら)と訓ず」とあります。 当時の寺院には付属的な建物として浴堂(風呂場)が、 設けられていました。 この浴堂での沐浴の際には、 肌を見せてはいけないと固く戒められており、 必ず単衣をまとって入浴していました。 これが「浴帷子」で、 別に「明衣」などとも呼ばれていました。 その素材の多くは白の生絹でしたが、 後には模様のあるものも用いられたようです。 この「浴帷子」は時代とともに「湯具」(ゆぐ) 「見拭」(みぬぐい)「湯巻」(ゆまき)「腰巻」など 様々な言葉が使われるようになっていきます。 呼び名が変るにともない、 用途も少しずつ変化していきました。 そして、江戸時代の中期には湯上がりのときに着る着物をいうようになりました。 幕末の浮世絵には浴衣をまとった美人図がたくさんあります。 湯屋での入浴がひとつの風俗として 定着していたことを示すものといえましょう。 こうした湯屋の発達は、 いきがる「江戸っ子かたぎ」とあいまって、 湯上がりに着る浴衣を質量ともに向上させることになりました。 さらにもうひとつ忘れてはならないものは、 芝居からの影響です。 歌舞伎十八番「助六」では、かんぺら門兵衛が 藍で染めた白地の真岡木綿 (今の栃木県真岡で産出した木綿)の浴衣をひっかけて、 帯をしないで登場してきます。 今では浴衣といえば、縁日、祭り、夕涼み、花火などとともに、 夏の風物詩として欠かせぬものとなっています。 こうした夏の普段着として浴衣が定着したのは、 明治に入ってからのことです。 |
東京釣用品協同組合 03−3831−1862 113−0034 文京区湯島3−23−8
関連リンク 銀座 東作


写真は 竿富 吉田 嘉弘さんの実演の様子 |
釣竿には、一本の竹をそのまま用いる「延べ竿」と、 何本かのたけを継ぎ合わせて一本の竿にする「継竿」があります。 継竿が出現したのは口伝によると 「平安時代末期の治承4年1180年に京都で発祥した」 とありますが、これを裏つける資料は現存していません。 しかし、京都が発祥地であることは、 江戸時代初期の延宝3年(1675)にだされた俳書の中に 「いれこ竿」が登場することからわかります。 一方、江戸における継竿の発祥は、京都より遅れ、 享保年間(1718−35)と思われ、 その製造技術が一大飛躍を遂げたのは、 江戸時代の天明8年(1788)に創業された 「泰地屋東作」に負うところが多いと言われています。 ちなみに、現代の江戸和竿職人の系譜を溯ると、 大部分の人が初代泰地屋東作にたどりつきます。 江戸和竿とは、何本かの異なる竹 (布袋竹、矢竹、淡竹、真竹)を継ぎ合わせて 一本の釣竿にする「継竿」のことをいいます。 和竿作りは、まず竹の選別から始まります。 竹林へ直接足を運び、一本一本吟味していきます。 良竹は、百本のうちせいぜい一本か二本ぐらいだといわれています。 その後、約一ヶ月天日で乾燥させます。 布袋竹、矢竹、淡竹、真竹一本一本の竿の調子を出すためには、 竿の設計図ともいわれる「切り組み」がもっとも重要です。 釣る魚、釣り方、釣り場、使用条件などを考えて、 もっとも使いやすい釣竿になるように竹を選定します。 |